招福兎行vol.13 妖刀村正
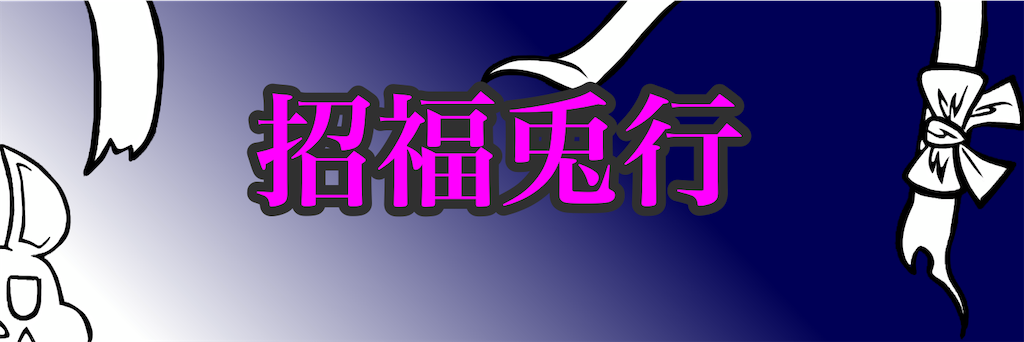
ー魔剣ー
その響きは厨二心を掴んで離しません。
そんな紫オーラ渦巻く怨嗟の魔剣の中から、今回は伝説の妖刀として名高い「村正」について調べてみました。
もくじ☟
名刀村正
千子村正(せんごむらまさ)
母親が千手観音に祈願し村正を生んだ事から、己を千手観音の申し子とし、千子の姓を名乗ります。
初代村正の最古の銘が1501年とされており、以降、数代に渡りその名を襲名する事により1668年の頃まで存続していたとされます。
名刀「正宗」に勝るとも劣らない「村正」の刀剣は、その切れ味の凄まじさから天下人や大名、上級武士に愛用される。
ふむ、なるほど。
歴史に名を残す人物や、セレブ侍まで幅広くその刀の虜になった訳です。
虚兎も画像で見ただけですが、その美しさたるや、まるで時が止まったかのよう。
しかし本来これはただの美術品ではありません。
当時はこれを腰に挿し、時として実際に抜いて戦ったのです。
こんな大きな刃物を振り回されたらと思うと恐ろしいですね。そんな時代の中、「村正」は絶大な人気を誇っていました。
まさに強さと美しさを兼ね備えた刀であると言えます。
妖刀村正
さて、程よく身体も暖まってきた所で、肝心の「妖刀」としての性質を見ていきましょう。
いかに村正が名刀だとしても、刀が一般的だった当時ならともかく、この現代でこれ程の人気を博しているのは「妖刀」と言う、なんかかっこいい感じの属性があるからに他なりません。
伝説の妖刀と語り継がれるゆえんとは一体何なのでしょう。
いつの時代も、人は神秘的なものに魅了されるものです。
そしてそれが忌むべき物であったとしても。
「村正」を語るに、こんな言葉があります。
一度抜いたら、血を見るまでは鞘に収まらない
誰の言葉ですか?
さぁ。わかりません。
ネッ…古文献を漁っている時に見かけた言葉です。
しかしまさに「妖刀」を象徴するかのようなキャッチコピー。
まさか、刀の邪悪な怨念が血を求めているとでも言うのでしょうか…
まさか…ね…
徳川家の厄災
村正の妖刀伝説は江戸時代から語りつがれていたようで、その理由は江戸幕府初代将軍 徳川家康。
そう。かの徳川(松平)家に由来します。
家康の祖父 松平清康(1511〜1535)
尾張(現・愛知県名古屋)守山城攻略の最中、家臣の阿部正豊の謀反に会い命を落とした。
家康の父親 松平広忠(1526〜1549)
岩松八弥の奇襲に会い、負傷する。
家康の妻 築山殿つきやまどの(不明〜1579)
岡本時仲と野中重政により自害を迫られ、それを拒んだため手を下される。
家康の嫡男 松平信康(1559〜1579)
織田信長の要求により、二俣城にて切腹をさせられた際、解釈(長く苦しむ事の無いよう、直後に首を切り落とす)に使われた刀。
徳川家康(1543〜1616)
2度に渡り怪我を負う。
以上の際に使われた刀や槍が、なんと全て村正銘だったとの事です。
徳川家の一族は村正によりことごとく負傷を負い、また命を落とす事になったのです。
まさに徳川家に向けられた怨念そのもの。
家康はこれを徳川家に仇なす刀として忌み嫌い、村正の携帯の禁止まで発令したとか。
家康は日光東照宮にて、東照大権現(とうしょうだいごんげん)と言う神として祀られております。
まさに神をも恐れぬ呪いの刃と言う事ができます。

写真はイメージです。村正ではありません。
虚兎の持っている模造刀、備前長船(びぜんおさふね)と、パナ○ニックの空気清浄機です。
真実はどちらに
真実とは時に残酷です。夢を奪い、ロマンを奪います。キラキラと輝いていた瞳はいつしか、突きつけられた現実を前に汚れきり、心は冷たく閉ざされてしまいます。
徳川家の災難の時代、村正の作る刀は以外にもどちらかと言えばリーズナブルな方で、決して高価な物ではありませんでした。
一説には、初代の村正は農耕具を製作していたようで、戦乱の時代に刀の需要を感じ、刀鍛冶に転職したそうです。
しかしその完成度の高さで話題になった村正は、武士達に好んで愛用される事となり、その時代けっこうみんな村正を持っていたようで、一連の徳川家の災厄に絡む「村正」と言う不気味な共通点も、つまりまぁありえる事だったとされています。
しかもたった1人の妻や子が被害にあったのなら呪いも現実的ですが、家康には妻も子も、正確な数はわかりませんが、少なくともどちらも10人以上はいたそうです。
村正本人にしても、とくに徳川家を呪う理由などなく、なんなら徳川家康本人も名刀と名高い「村正」を何本も所持していたとされています。
……ふむ。
…なるほど。
誰ですか…
血を見るまで鞘に収まらないとか言ったやつ。
なんとも恐ろしい話です。
癒しまんが

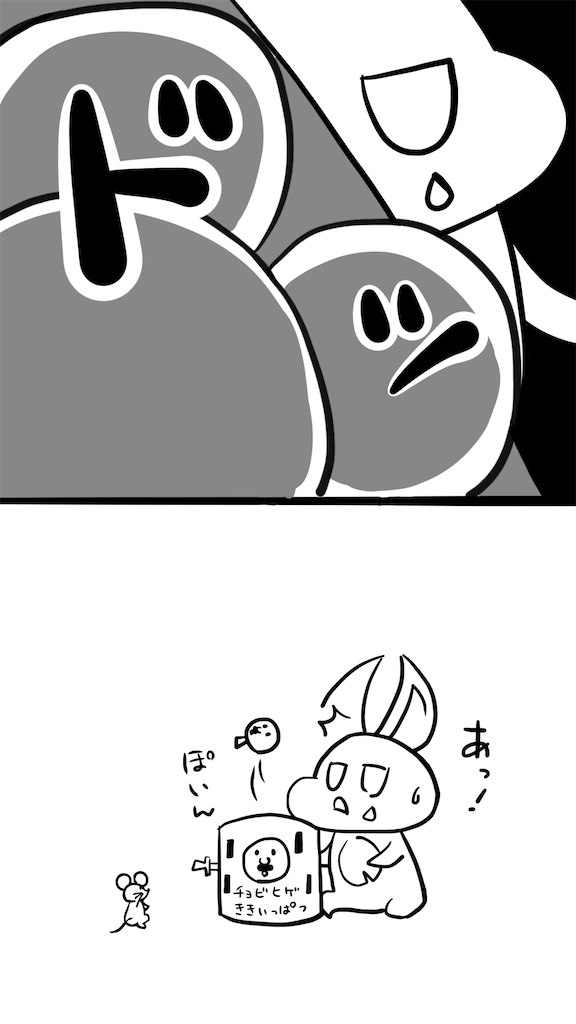
お読み頂きありがとうございます☆
presented by 虚兎
©️2020 虚兎